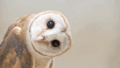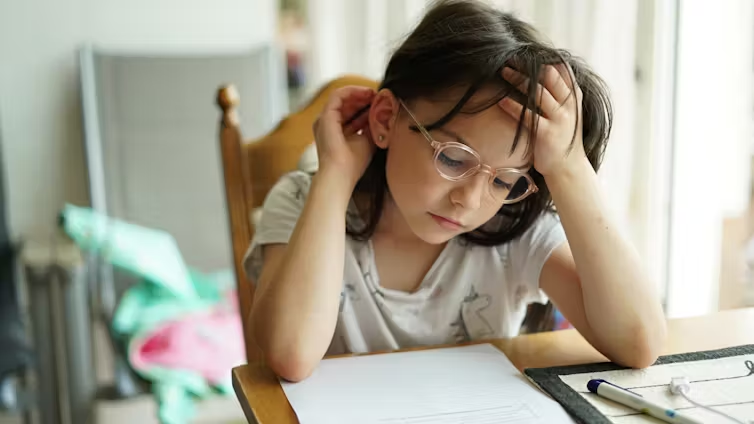

[公開日}:2025年9月10日 午後10時57分(オーストラリア東部標準時)
[質問] : グレース、9歳、ベルファスト、英国 北アイルランド
[答えてくれる先生]:James Williams
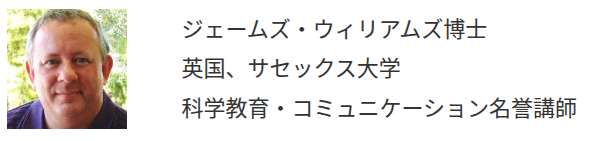
❝学校で一日中過ごしているのに、なぜ宿題をしなくてはいけないのでしょうか?❞
宿題 (homework) に行き詰まって、ノートをじっと見つめた経験があるなら、それはあなただけではありません。多くの子どもたちが、宿題があるとストレスを感じたり、退屈になったり、不安になったりすると言います。学校で何時間も勉強しているのに、なぜ先生は家でする宿題を出し続けるのでしょうか?
利用可能な研究によると、中・高等学生 (secondary school students) の場合、よく練られた宿題は、数学 (maths) や英語 (English) などの科目で約5か月分の学習成果を伸ばす効果があることが示されています。小学校 (primary school) では、その効果は約3か月と小さくなりますが、それでも有益です。
宿題は、学んだことを実践し、記憶を定着させ、時間管理や自立といったスキルを身につけるのに役立ちます。
しかし、研究によると、宿題に対する感じ方はいくつかの要因によって異なることが分かっています。宿題が退屈だと感じる場合、それは課された活動自体が本当に退屈なだけかもしれません。すべての宿題が同じではありません。
授業内容と関連のないワークシートはあまり役に立ちません。考え、創造し、概念やアイデアを探求する課題の方がはるかに効果的です。
教師は、課題の内容とその説明方法について深く考える必要があります。課題が明確に説明され、生徒が役立つフィードバックを得れば、課題を完了する可能性ははるかに高くなります。教師はまた、宿題を単なる追加課題 (extra work) ではなく、学習の一部 (part of learning) として捉えられるような、意味のある課題を選ぶ必要があります。
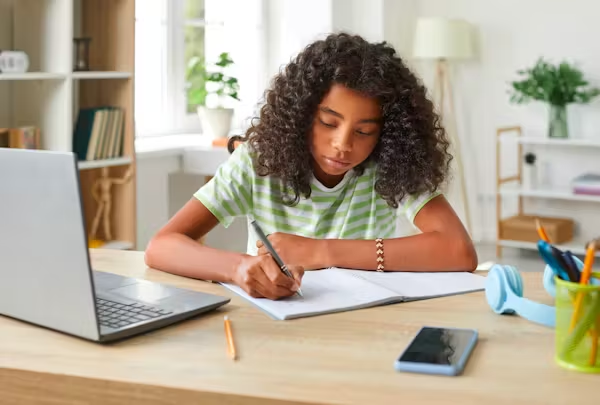
創造的な宿題や、自分の情熱に関連した宿題は、より楽しくなります。そして、成功への思いが芽生えます。課題が不可能に思えると、諦めてしまいがちです。最後に、宿題に意味があるかどうかが問題です。授業で学んだことと関連した宿題は、より有益だと感じられます。
科学の教師として、私はいつも宿題を授業の最後ではなく、早い段階で出すようにしています。何が期待されているかを知っておくことで、生徒は課題をよりよく理解し、授業で取り組んでいることと関連付けて考えることができます。
宿題の進め方
宿題に対する姿勢は、課題そのものだけでなく、周りの人たちにも左右されます。親や保護者が励ましてくれたり、時間配分を手伝ってくれたり、宿題に興味を持ってくれたりすれば、宿題はより前向きなものになるでしょう。とはいえ、親が宿題をやったかどうか尋ねるのは良いことですが、実際に手伝うことは必ずしも有益ではないという研究結果もあります。
中には、より大きな課題に直面している子どもたちもいます。誰もが静かに勉強できる場所や、家で手伝ってくれる人がいるわけではありません。これは「宿題ギャップ: the “homework gap”」と呼ばれ、子どもたちが学校について不公平だと感じる可能性があります。
宿題を出すかどうかは学校次第ですが、宿題のあり方を根本から見直している学校もあります。より取り組みやすく、創造的な宿題を目指しています。すべての教科で宿題を義務付けるのではなく、任意とする学校もあります。また、宿題を誰にとっても公平なものにする方法も模索しています。例えば、友達と一緒に助け合いながら取り組める宿題クラブなどです。
宿題はすぐになくなるものではありません。でも、必ずしも負担になる必要はありません。適切に設計され、教師や保護者のサポートを受け、学習と結びついていれば、生徒としてだけでなく、考える人としても成長することができます。
ですから、次に宿題に取り組むときは、「この宿題から何を学べるだろうか?」と自分に質問してみてください。もし難しすぎたり、無意味だと感じたら、遠慮なく先生に意見を言ってください。あなたの意見は大切です。

この記事は、クリエイティブコモンズライセンス(CCL)の下で The Conversation と各著作者からの承認に基づき再発行されています。日本語訳は archive4kids の翻訳責任で行われており、The Conversationによる正式な翻訳ではありません。オリジナルの記事を読めます。original article.